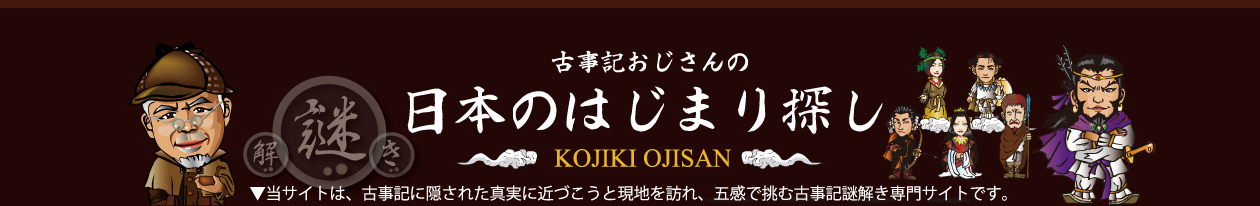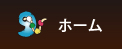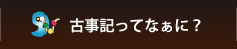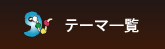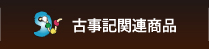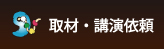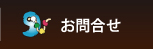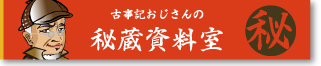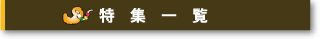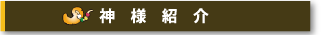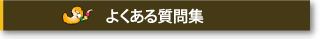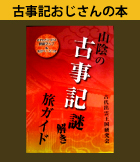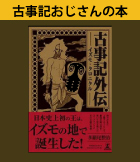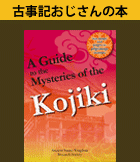杵築大社の造営は、「出雲国造家」を拝命した神魂家が、出雲一帯から人と資材を拠出させたと考えるのが自然ではないでしょうか。
659年に造営命令が出され、798年に「出雲国造家」が杵築地方に移ったということは、その間に完成した訳です。しかしいつ完成したかは、はっきりしません。
現在平成の大遷宮工事の真っ最中ですが、現代の輸送能力や技術によっても年単位の仕事です。全てを人力に頼っていた古代なら10年単位の仕事だったはずです。
伝えられるように、現在の規模より遙かに大きな建物であったなら、軽く見積もっても50年以上の時間が必要だったはずです。
この造営に必要な資材集め・加工・建設を地元の人力で行ったと思われますから、地元即ち古代出雲王国地方の負担は過酷なものであったと想像できます。
これは江戸時代の参勤交代同様に、勝者が敗者を疲弊させる手段だったのではないかと考えます。
大社は何度か倒壊し、建て直されたと伝えられています。その度に再建を強いられれば、古代出雲王国地方が、中央権力に対抗するエネルギーを蓄積することは不可能であったはずです。
時の中央権力にとって「古代出雲王国」とは、こうまでして押さえつけなければならない程に脅威を感じさせる存在だったのではないでしょうか。